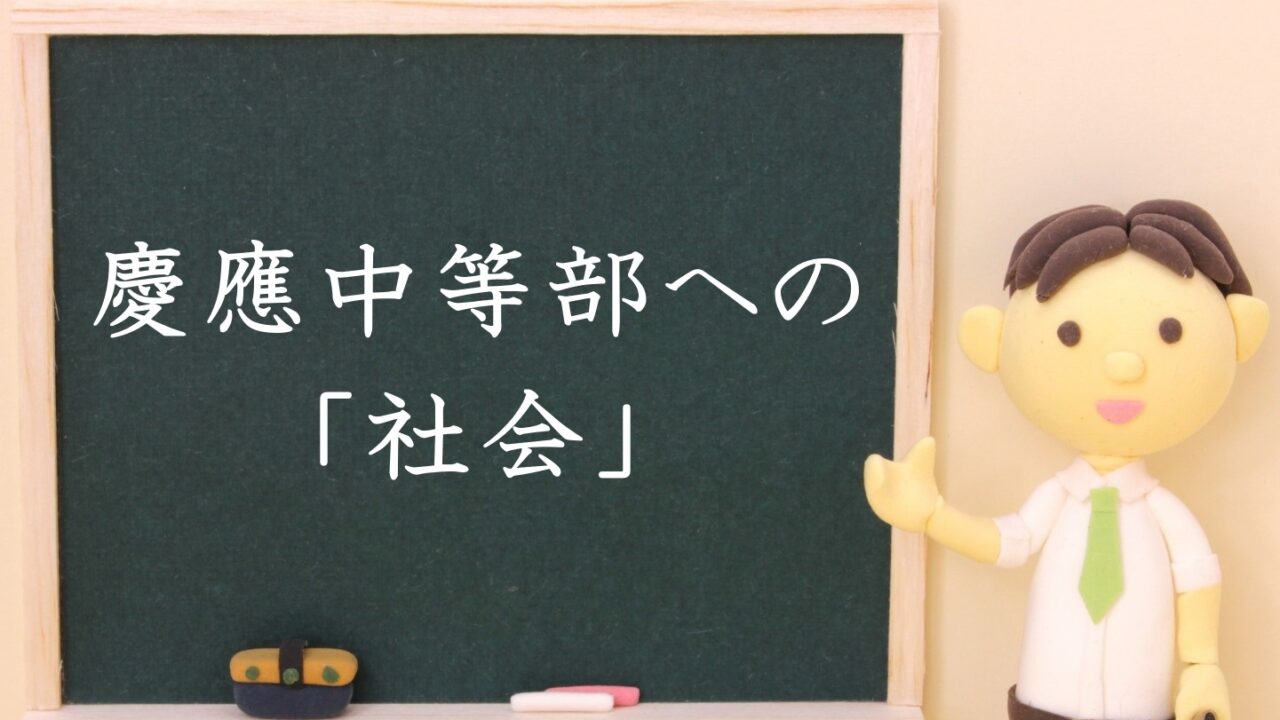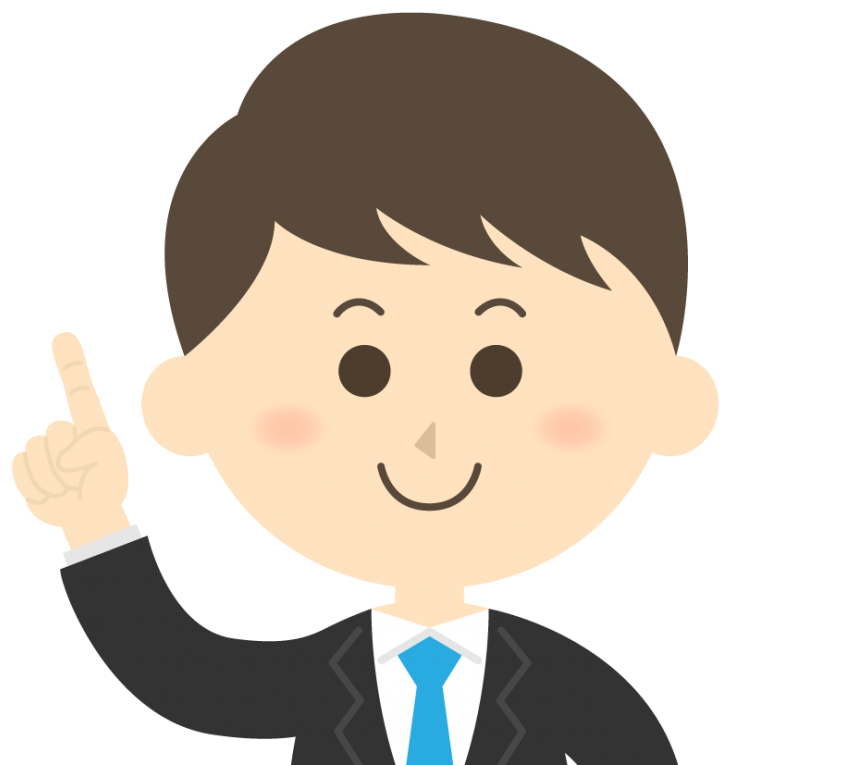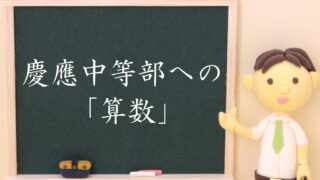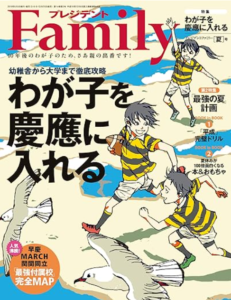このブログは、慶應付属中専門の塾講師・家庭教師をしているたくと( @tact_roadtokeio ) がお送りしております。
みなさんこんにちは!
今回から3回に分けて、慶應義塾中等部の社会に向けた勉強の仕方・意識の持ち方について書いていこうと思います(もしかしたらもう少し増えるかも)。
そして第1回目の今回は、
中等部社会で合格点を取る(=慶應中等部の求める人物像になる)ために、「できるだけ早い段階で意識すべきこと(意識しなきゃいけないこと)」
についてです。(「できるだけ早い段階」で意識すべきことなので、学期初めの4月に書いています。)
慶應中等部だけでなく、慶應普通部や慶應湘南藤沢中等部志望の方にとっても意味のある内容だと思うので、ぜひ最後まで読んで見てくださいね。(おそらく筑駒・御三家など最難関校を目指す子にも意味があるかと思います。)
ではでは、いってみましょう!
まずは社会の学ぶ上での「誤った前提」を把握しよう。
さて、これから慶應中等部に向けた社会の学び方・意識の持ち方について書いていきますが、何よりもまず最初にやるべきことがあります。
それは、「『社会の学び方の前提』が大きく間違っている」ということを把握し、改善することです。
本当に多くの受験生が、「社会の学び方の前提」をそもそも間違えている。「多くの受験生」が間違えているということは、その集団の中にいると、誤った前提の中で学んでいるということになかなか気づけないわけです。よって、その誤った前提を修正すること自体が、周りの受験生との大きな差別化に直結します。
というわけで、その「誤った前提」について見ていきましょう!2つあります。
誤った前提①-「社会は暗記科目だから後回し」では通用しない
よく、「社会は暗記科目だから、小4・小5のうちは算数と国語を大事にしてください。社会は小6からでも間に合います。」と言う先生がいます。そしてその教えを受け入れ、「社会は暗記科目だ」、「社会は小6から詰め込めば大丈夫!」と思ってしまう子もたくさんいます。
この意識が慶應中等部をはじめとする最難関校の合格を遠ざけてしまいます。
なぜか?
それは、「そもそも、僕らはなぜ学んでいるのか?」ということを考えれば自ずと分かります。
僕らは、小学校(6年間)・中学校(3年間)・高校(3年間)・大学(4年間)と約16年間も学びます(大学院に行けばさらに長い)。人生の16年間もの時間を費やす学びを「受験のため」という自己の利益のために学ぶというのはナンセンスなわけで(→中等部の国語の問題でも同じ内容の問題がありましたね)、この社会で活躍しうる人材になるため、単純化して言い換えれば「社会のため」に学んでいるわけです。
(「いやいやそんなことないよ」という個々の考え方は尊重されるべきですが、今回はその考え方は主題には成り得ず、あくまで中学校側は「社会のため」を前提に教育を行っているというのがポイントです。)
つまり、人生の16年間も費やす学びにおいて、僕らが活躍しようとする「社会」を知るということは最も根底にあるべきことなわけで、言い換えれば、その「社会」を学ぶ科目(=科目としての「社会(科)」)というのは、どの科目よりも最も根底にあるべきものなわけです。
そしてその前提に立つならば、「社会」という科目は、何かを「暗記する科目」ではなく、自分たちがどういう社会を目指すべきかと「思考する科目」であることは自明でしょう。最低限覚えるべきことはもちろんありますが、主題はそこではない。それらはあくまで思考するためのピースにすぎません。
少し深掘りしておきます。
僕らが生きる現代社会は、科学(科学技術)によって支えられています。
その科学そのものの理論や論理を学ぶのが「理科」です。
また、科学というのは「数学」という言語によって記述されています。その数学の序章として僕らは小学生のうちに「算数」を学びます。(算数は、野球で言えば「グローブの使い方」について学んでいるようなもの。グローブのことを知っただけで「野球なんてつまらない嫌い!」というのがナンセンスなように、算数をやっただけで「数学なんて不必要だ!」というのは超ナンセンス。)
さらには、科学という「論理」によって構築されている学問を追求していくと、僕らは感性的な問題や倫理的な問題にぶち当たります。なぜなら、科学は、感情のような主観性を排除した学問だから。よって、科学を追求するならば、並行して感性や倫理観を養っていく必要があるわけです。その感性・倫理観を養ううえで役立つのが「国語」の読解(特に「物語文」や、感性や倫理性について書かれた「説明文」)と言えるでしょう。
こんなふうに、算数も理科も国語も、「科学によって支えられている社会」という土台の上になりたっている科目(学問領域)であり、「科学によって支えれている社会」にとって重要だから、義務教育の中で全員が学ぶわけです。(もし社会が科学ではない別のものによって支えられるようになれば、算数や理科は主要科目ではなくなるでしょう。)
すなわち、算数や理科や国語の根底にあるのが「社会」なわけです。(大事だから2回目。)
なので、全ての科目に先立って、根底にある「社会」への意識を強く持つ必要があるわけです。だから、「社会」という科目を後回しにするのはナンセンスで、むしろ何よりも先だって学ぶ必要があるわけです。そしてそれを、中学側(特に難関校になればなるほど)は受験生に求めています。(これは慶應においても同様。)
【まとめ①】
・「社会」はすべての科目の根底にある科目であり、自分たちがどういう社会を目指すかを「思考する科目」である。
・よって、「社会は暗記科目」と捉えて後回ししていいという前提を捨てるべき。何よりも先だって学び、「思考」していくべき科目である。
誤った前提②-「時事は直前期でいい」では通用しない
前章では、全ての科目の根底にある「社会」への意識を強く持つ必要がある、ということを書きました。
では、その「社会」への意識を強く持つうえで必要なこととは何なのでしょう?
これは、初対面の人を知るときのプロセスに似ています。
初対面の人にあったら、まずは話してみる。ある意味、「今のその人」を知ることがスタート地点になるわけです。そしてその上で、もし必要あれば昔の話をして「過去のこと」を聞くし、将来どういうことをしたいのかという「未来の話」もする。
社会のことを学ぶ際も同じで、まずは「今、社会で起きていること」を知ることが大切なわけです。そして必要あれば、過去のことを学ぶ。そしてそれらを用いて、未来の社会を想像したり、未来の社会の理想を考える。
つまり、「今、社会で起きていること」を知ることが何よりもまず大切なわけです。これは言い換えれば、「時事(=今その時の社会で起こっている出来事)」について日々キャッチアップしていくことが大切で、すなわち「今の社会で何が起きているかを知ろうとする『社会に対するアンテナ』を立てること」が大事なわけです。
でも、多くの塾では、小4から学年が上がるにつれて「地理→歴史→公民」と学んでいって、直前期になってやっと「時事」について学びます。この方針では、「時事」という社会に対するアンテナを立てる作業を直前期にやることになる。言い換えれば、社会に対するアンテナを立てずに数年間社会を学ぶわけです。(先述の例で言えば、目の前にいる相手を知るために、その人が「今どんなことを考えているか・今どんなことを感じているか」は聞かずに、過去のことばかり聞いたり、未来のことばかり聞いているような状態になってしまう。)
この「時事は後でいい」という前提を捨てる必要があります。
重要なのは、「社会に対するアンテナ」をしっかりと立てて「今の社会(=時事)」と毎日向き合いながら、それと並行して地理・歴史・公民を学んでいくことです。「今の社会(=時事)」を見ずに地理や歴史や公民を学ぶことはナンセンスです。
【まとめ②】
・「社会」を学ぶ上で最も重要なのは「今の社会(=時事)」と毎日向き合うこと。
・よって、「時事は直前期に学べばOK」という前提は捨てるべき。時事をまず何よりも大事にし、そのうえで地理・歴史・公民を学ぶのが重要。
慶應中等部が求めるもの
すこし長くなったので以上のことを改めて整理すると、慶應をはじめとする難関校を目指して社会を学ぶうえで必要なことは、
- 「社会」という科目は、全ての科目の根底にある。(→後回しにすべき科目ではない)
- その「社会」を学ぶ上で最も重要なのは、社会の今を学ぶ「時事」。
の2つということです。(これらは、過去問を見れば分かると思いますが、慶應中等部では特に求められており、社会だけでなく国語や面接・志願書にも大きく響いてきます。)
そしてこれら2つのことを言い換えれば、慶應中等部が受験生に求めているものというのは、「社会に対する”アンテナ”を持っているか否か」ということだと言えるでしょう。「この子は普段から社会に関心を持っているのだろうか?」ということですね。(ここまで書くと、慶應を志望している方であれば福澤諭吉の生涯を思い出し、その生き方とリンクしていると感じられる人も多いのでは?)
【慶應中等部が受験生に求めるもの】
「社会に対する”アンテナ”を持っているか否か」
(普段から社会に関心を持っているかどうか)
この「社会に対する”アンテナ”」を持って生活していると、「今、社会で何が起こっているか」を常に把握しながら生きることになります。
すると、その「今の社会」に繋がるすべての科目が有機的に結びついてく。それが「机上の知性」ではなく「真の知性」となる。これが慶應中等部が求めている受験生への条件です。そういう子が入学してくれたら、先生に依存せずに自ら、もしくは仲間たちとともに学んでいってくれる。こんなふうに「独立自尊の精神」を獲得しているかどうかが社会の学び方・捉え方に現われるわけです。
どうです?ちょっと「社会に対するアンテナ」を立ててみようと思えましたか?
「社会に対するアンテナ」を持つための具体的方法
では、「社会に対するアンテナ」を持つには、具体的にはなにをしたらいいのでしょうか?
ここまでは学びを多く詰め込むために文章量を多くして書いてきたので、ここからは簡潔にその具体的な方法について書いていきます。特に、ご家庭でできる取り組みに絞って2つほど書きますね。
具体的方法①:「子ども新聞」の活用〈★最重要〉
社会に対するアンテナを持つための具体的方法の一つ目は、「新聞を読むこと」です。
これはもはや「オススメ」を越えて「義務」に近いくらいの感覚です。実際、自分がこれまで指導してきた生徒さんで慶應中等部に合格した子は全員(「ほぼ全員」ではなく本当に「全員」)が日常的に新聞を読んでいます。
とはいえ、大人向け新聞はなかなかハードルが高い(日経新聞を読んでいる子もたまにいるけど)ので、オススメなのは時事をやさしく&分かりやすく書いてくれている「子ども新聞」の活用です。特に以下の2つがオススメです。(各新聞へのリンクを張っていますが、極力購読料が安くなるものを選んでいます)
1つ目は、「読売KODOMO新聞」です。
【 読売KODOMO新聞 ![]() 】
】
〈オススメポイント〉
① 月額550円(税込み)とかなり格安。
② 週1日(毎週木曜)発行なので習慣に組み込みやすい
③ 1週間の出来事がまとまっているので読みやすい。
④ 知的好奇心を広げてくれるような特集記事が多い。
お申込みはこちら⇒「 読売KODOMO新聞 」
2つ目は、「朝日小学生新聞」です。
【 朝日小学生新聞 】
〈オススメポイント〉
① 毎日発行のため「今社会で起きていること」を毎日学べる。
② 毎日発行なのに月2,100円(税込)とリーズナブル。
③ 楽天市場だと楽天ポイントが付くため新聞なのに実質値引きされる。
④ 楽天市場だと3か月単位で申し込むので、解約する場合も申し込み不要。
⑤ こちらも知的好奇心を広げてくれるような特集記事が豊富。
お申し込みはこちら⇒「 朝日小学生新聞 」
まずは読んでみたいと思える方を購読してみるのがいいかと思いますが、最も効果的な使い方としては、
① 毎日発行の朝日小学生新聞を毎日読んで日々の社会の動きを学び、
② それらの学びを木曜発行の「読売KODOMO新聞」で総復習する。
という使い方です。この使い方だと、1週間で時事を2回学んだ状態になり、「直前期の時事問題対策」に費やす時間が大幅に短縮されるため、直前期に他の科目に時間をさけるというメリットがあります。
そしてさらに、
③ 新聞で知ったこと・学んだことを元に親子で会話する。
までできると最高です(これは家庭教師の先生や個別指導の先生にアウトソースするのも可)。
ちなみに、子ども新聞を購読し始めた親御さん(特にお母さん)によく言われるのは「『子ども新聞』って少しなめてましたが、読んでみるとすごく分かりやすくて、子どもよりも自分の方が学んでます!(笑)」といったことです。子どもだけじゃなく親も一緒に学んで、日々その学びを共有したら、そりゃ社会を好きになって得意になっていくよね、という気がします。
具体的方法②:ニュースや気づきを「生活」と結びつける
社会に対するアンテナを持つ具体的な方法の2つ目は、「ニュースや気づきを『生活』と結びつける」ことで、これは例えば以下のようなことです。
「スーパーの野菜もお菓子も高くなっているね」
→なんでだろう?
→円安?天候?物流?間違えてもいいから考えられる要因を挙げてみる。
→どれが正解かを親子で(もしくは先生と)調べてみる。
「災害が起きたら、電気ってどうなるの?」
→今、この瞬間に大地震が起きて電気が止まったらどうする?
→事前にできる対策や事後にできることを考えてみる。
→そこから話を拡張させて、再生可能エネルギーの話をしてみる。
といった形で、生活の中の気づきやニュースを見て感じた疑問をきっかけに「(自分の)生活」と結びつけていきます。気づきのきっかけとしては、上記で紹介した「子ども新聞」で読んだこと・学んだことを活用するのもいいでしょう。
この目的は、社会という科目を「教科書の外」に出して、自分のいる「生活」に結びつけることで「自分事」に変えることです。この作業によって、「社会に対するアンテナ」は強く太いものになっていくわけです。
まとめ:「社会に対するアンテナ」を立てて学んでいこう!
では最後に、まとめとして。
「社会」という科目を学ぶ上で、「社会に対するアンテナ」を立てることが非常に重要です。「社会に対するアンテナ」を立てて学んだこと・考えたことは、慶應中等部の社会で合格点を取ることに大きく貢献してくれるでしょう。
でも、最も強調したいのはそういった「受験的側面」のために必要だと言うことではありません。
「社会に対するアンテナ」を立てて学ぶことは、「受験生」としてではなく「一人の独立した”大人”」へと成長することに大きく貢献してくれます。「一人の独立した”大人”」として、社会について親子で、先生と、仲間と語り合えるようになるわけです。語り合った結果、本人が「理想の社会」というものを少しずつ具体的にイメージできるようになり、その「理想の社会」のために自分自身は今後何をやっていくべきかということを具体的に考えていけるようになるわけです。
「一人の子ども」が「独立した大人」になるために「社会に対するアンテナ」を立てられるよう、周りの大人がしっかりサポートしていきましょう。今回の記事がそのきっかけに少しでもなれたら嬉しいなと思います。
.
というわけで、今回はこのあたりで。
もしまた読みたいと思っていただけましたら、ブログのブックマーク、もしくは更新情報を投稿しているX(旧twitter)のフォローをよろしくお願いいたします。また、指導依頼に関してはもX(旧twitter)のDMにご連絡いただければと思います。
【X(旧twitter)】
・ たくと@慶應付属中専門の塾講師・家庭教師
( @tact_roadtokeio )
ではでは、読んで下さってありがとうございました。
また次回、お会いしましょう!
【 読売KODOMO新聞 ![]() 】
】
〈オススメポイント〉
① 月額550円(税込み)とかなり格安。
② 週1日(毎週木曜)発行なので習慣に組み込みやすい
③ 1週間の出来事がまとまっているので読みやすい。
④ 知的好奇心を広げてくれるような特集記事が多い。
お申込みはこちら⇒「 読売KODOMO新聞 」
【 朝日小学生新聞 】
〈オススメポイント〉
① 毎日発行のため「今社会で起きていること」を毎日学べる。
② 毎日発行なのに月2,100円(税込)とリーズナブル。
③ 楽天市場だと楽天ポイントが付くため新聞なのに実質値引きされる。
④ 楽天市場だと3か月単位で申し込むので、解約する場合も申し込み不要。
⑤ こちらも知的好奇心を広げてくれるような特集記事が豊富。
お申し込みはこちら⇒「 朝日小学生新聞 」