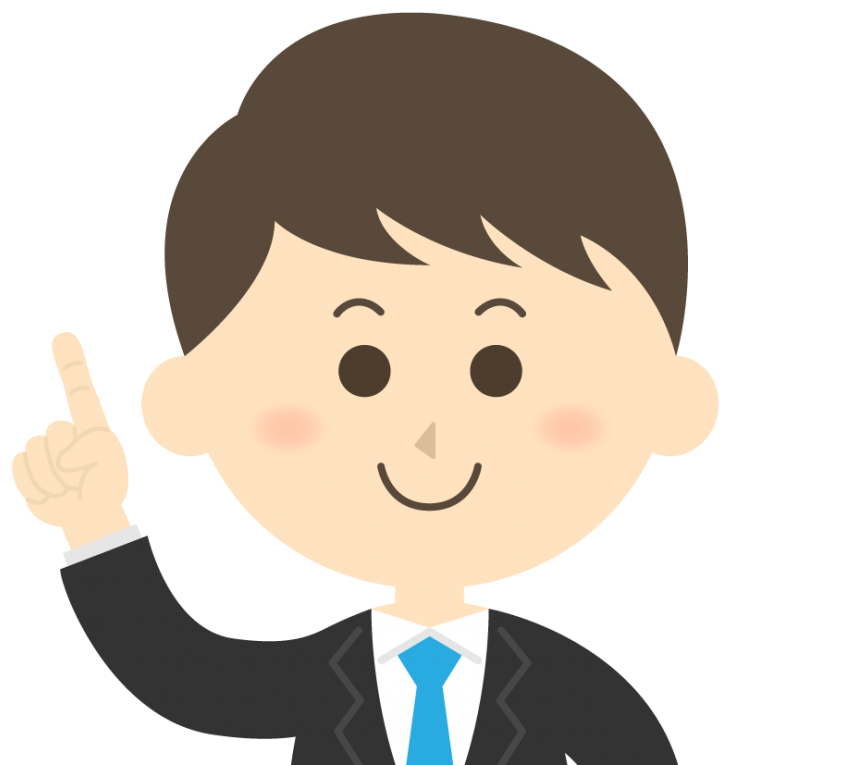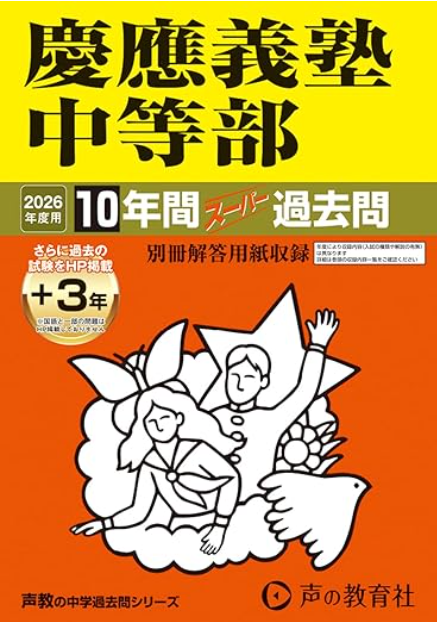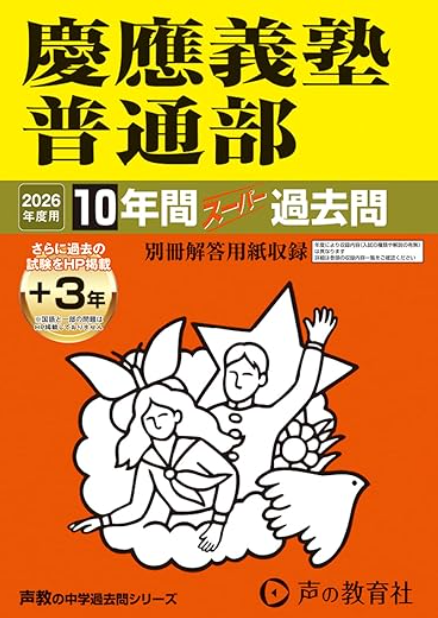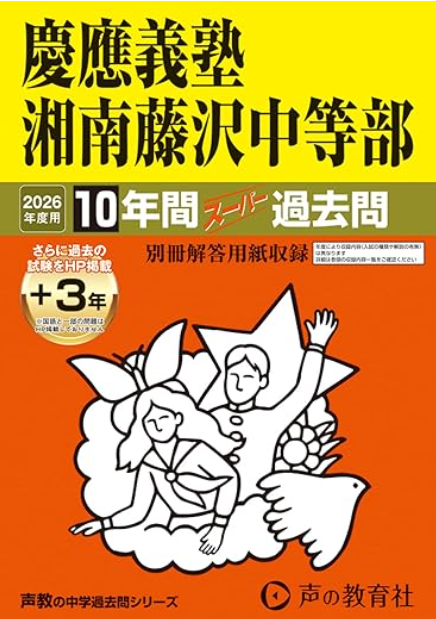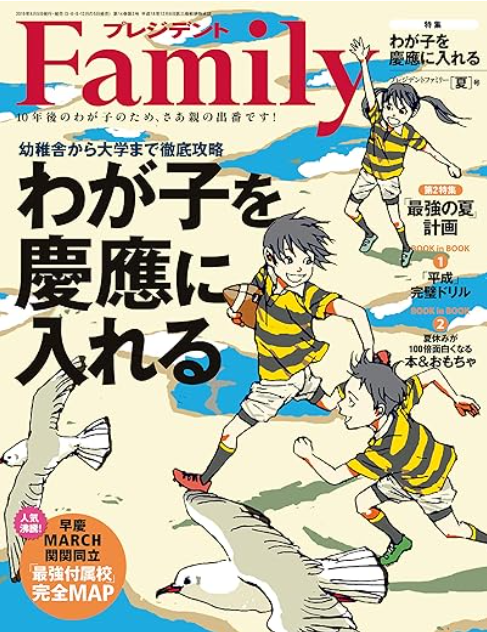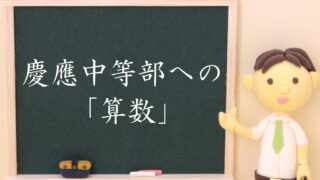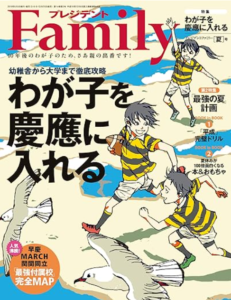このブログは、慶應付属中専門の塾講師・家庭教師をしているたくと( @tact_roadtokeio ) がお送りしております。
さてさて、今回は過去問について。
この記事を書いているのは4月なので、人によっては「過去問はまだ先じゃない?」なんて思う方もおそらく多いでしょう。なぜなら、多くの塾で「過去問に手を付けるのは9月以降、それまでは絶対に手を付けないでください!」と言いわれているからです。
でも、この意識は慶應付属3中学を目指すうえで大きなマイナス要因として働きます。特に慶應中等部の場合に。
なので、僕が指導している慶應志望の生徒さんには、学年に関わらずできるだけ早い段階で必ず過去問に目を通すようにしています。
とはいえ、「解けないのにどうやって過去問を使うんじゃい!」と思っている方も多いと思うので、今回は慶應付属3中学を目指す受験生とその親御さん向けにとって必要な過去問の使い方について見ていきたいと思います。
今回の記事を読むことで、塾の過去問使用の方針に従っている他の受験生よりも大きくアドバンテージを得ることができるはずです。慶應志望でなくても、難易度の高い学校になればなるほど今回の内容は参考になると思うので、ぜひ読み進めてみて下さいね。
ちなみに、2026年度入試用の過去問は、慶應義塾中等部・慶應義塾普通部の過去問がは3月28日にすでに発売されており、慶應義塾湘南藤沢中等部の過去問もまもなく発売予定です(4月21日)。早めに手に入れておきましょう。
.
「過去問は9月から」という意識が合格率を下げる
さて、先述の通り、塾に通っている生徒さんやその親御さんは、「過去問は9月から!それまでは絶対見ちゃダメ!」と塾から強く言われているケースが大半です。そして真面目で塾の方針に忠実な方ほど、その教えをしっかり守り、夏休みの終盤から過去問を購入し、9月に備えます。
しかし、9月から過去問に手を付けはじめ、10月過ぎになると、こんな声が続出します。
「塾でやって来た内容と全然と違うんですけど!」
「これだと塾のテキストの復習をしても意味がないような気がします。」
「これから一体なにを使って学べばいいんでしょうか?」
この傾向は志望する学校が上位であればあるほど強くなります。(直前期に助けを求めて連絡下さる方からは高確率で上記の声を聞きます。)
まぁでもこれって、普通考えたら当然な話ですよね。だって、どんな問題が出るのかを知らずに小4から小6の夏まで学んできたのだから。
この「どんな問題が出るのかを知らずに学び続ける」という姿勢は、中堅校までであればそれほど問題になりませんが(オーソドックスな問題を中心に出題されるため)、難関校になればなるほど大きな不利要因として働きます(学校ごとに求める思考力・知識の粒度が異なるため)。
そしてこれは、慶應付属3中学にも当然当てはまります。特に慶應中等部では。
集団塾のカリキュラムやテキスト構成は、最終的には過去問で64%くらい得点できるようになる構成になっています(8割の問題を解くことができ、そのうち8割を正答できるようになるイメージ。)
これは多くの学校ではボーダーライン周辺の得点率です。
しかし慶應中等部の場合は、どの科目も8割以上を取る必要があります。それなのに、塾の最大公約数的なテキスト・カリキュラムに従って学び、さらには過去問を通して「何が必要とされているかを直前まで確認しない」という姿勢は、どう考えたって合格から遠ざかる行為になります。
9月になって初めて過去問を確認して、「これから何をすべきか」をやっと確認できたとしても、残り半年もないわけです。
本気で目指すのなら、本気で対策をする必要があり、そのために必要不可欠なのが「過去問を通して学校が求めているものを把握すること」なわけです。
過去問には3つの使い方がある
過去問を早期に活用すべきという必要性についてはある程度お分かりいただけたかと思います。
では、具体的には過去問をどのように活用していくべきなのでしょう?
「過去問」と一言で言っても、その使い方には実は3パターンほどあります。
3パターンというのは、「縦に使う」・「横に使う」・「学校側からのメッセージを読みとる」の3つです。(これらは、あくまで個人的な呼び方です。)
使い方①:過去問を「縦に使う」
過去問の1つ目の使い方は、例えば慶應中等部の過去問を使う場合で言えば、2025年度の算数を通しで解いて、次に国語を通しで解いて、次に理科、次に社会、というふうに、各年度の各教科を「時間を計って通しで解いてみる使い方」です。
この使い方の目的は、「現時点で何点取れるかを見ること」です。
先述の「過去問は9月から」という、多くの塾が過去問に対してとるスタンスはこの使い方のみを想定したものです。「現時点で何点取れるかを見ること」が目的なら確かにそうかもしれませんが、過去問の最も有用な使い方は後述する「3つ目の使い方」の方なので、「9月から」というメッセージに従うのは合格を目指すうえで大きなネックになってしまいます。
使い方②:過去問を「横に使う」
過去問の2つ目の使い方は、「特定の分野(強化したい分野・弱点分野)のみを扱った問題をピックアップする使い方」です。たとえば、社会の公民分野の中でも「日本国憲法が少し苦手だな」と思っていたら、慶應中等部・普通部・湘南藤沢中等部で「日本国憲法をテーマにした問題」だけを年度を跨いでピックアップして解いていくイメージです。(なんなら学校を跨いでもいい。)
この使い方の目的はもちろん、「特定分野の教科・苦手分野の強化」です。
この使い方は、学年を問わずに採用可能です。たとえば、小学4年生の社会で都道府県を学んだら、慶應付属3中学で出題された「都道府県に関する問題」だけをピックアップして解いてみる、といった使い方をすることで、「今日学んだことが志望校では実際にどのように出題されているのか」を把握することができるわけです。
できるだけ早い段階からこの使い方をすると、小6の夏の段階では志望校が問うレベルを受験生本人が把握できている状況を作ることができ、直前期に何を学ぶべきかを自分ごととして考えられるようになります。これは慶應の「独立自尊」に沿った成長であり、より慶應に近づくことができるという副次的なメリットがあります。
使い方③:過去問を「学校側からのメッセージの読み取りに使う」
過去問の3つ目の使い方は、「学校側が受験生に求めるメッセージを含む問題をピックアップして解く使い方」です。
例として1つだけ挙げてみると、例えば慶應普通部では過去にこんな問題↓が出題されました。
【慶應義塾普通部過去問】
「あなたが勇気づけられた本の名前と、その本のどのようなところに勇気づけられたかを50字以内で書きなさい。」
この過去問演習から僕らが学ぶべきことは、「この問題で何点取れるか?」という現状分析ではなく、「慶應普通部は、本から学ぶことのできる受験生を求めているんだ!」という学校側からのメッセージの方でしょう。
このメッセージを早期に受け取れていれば、塾のテキストだけでなく「本を通して学ぶ」という習慣を比較的余裕のある時期から日々の生活に組み込むことができる、言い換えれば慶應側が求めている人物像に自分を近づけることができるわけです。一方、このメッセージを直前期に知ったところで、「本を通して学ぶ」という習慣を生活に組み込むことは現実的にはかなり難しく(残り日数が少なく時間的余裕がないため)、慶應側が求めている人物像には近づくことはできないわけです。結果、「それっぽい答え」を書いてかわすような過去問演習を繰り返すことになります。
以上からも分かるように、この3つ目の過去問の使い方の目的は、「慶應側のメッセージを受け取り、慶應に相応しい人物に自分を近づけること」です。そしてこの3つ目の使い方が過去問の使い方の中でもっとも重要なわけです。
だから、学年に関わらずできるだけ早期に、この3つ目の使い方で過去問に取り組む必要があるわけです。(少し皮肉的に言い換えれば、塾が発する「過去問は絶対小6の9月から」というメッセージはマイナスの差別化要因となり、この3つ目の使い方を早期からしている受験生からすると、周りの受験生との差が勝手に開くような”ありがたいメッセージ”となっているわけです。)
.
(また、この「3つ目の使い方」の拡張版の使い方を以前の記事で書いているので、ぜひご参考ください↓。内容はけっこう重複しているかも。)
「3つの過去問の使い方」の使い分け。
以上のように、過去問には主に3つの使い方があります。では、この3つの使い方自体は、どのように使い分けるべきでしょうか?
これは、生徒さん各々の学年や理解度に応じて変わってきますが、ポイントとしては、
「使い方①」は、「これまでの自分のやってきたことの結果のチェック」としての役割
「使い方②」と「使い方③」は、「これからの自分の成長・強化のため」の役割
ということです。言い換えれば、
「使い方①」は過去志向であり、
「使い方②」と「使い方③」は未来志向
なわけで、それを踏まえると先手先手で「使い方②」「使い方③」を行い、その結果の収穫として「使い方①」を行うという流れが理想です。
以上を踏まえた理想的な使い方(あくまで一例)としては、以下のように流れがオススメです。
- 小4から各単元の学習が終わったタイミングで、「使い方②」で過去問を活用して単元強化をする。(その結果、志望校の求めているレベルの把握もできる。)
- 週に1回、「使い方③」で活用できる過去問を先生(もしくは親御さん)がピックアップし、生徒さん(お子さん)と「こんなことが求められているんだね」というコミュニケーションを取りながら「慶應の求める人物像」と「どんな学び方が必要か」を把握していく。
- 学習が一巡したタイミング(小6の夏前後)に「使い方①」で過去問を活用して、現時点での自分がどのくらい得点できるか(学習の習熟度)を把握する。
→弱点分野が見つかれば、「使い方②」で単元強化する。
(①と②は併行して進めるイメージです。)
これを見ればお気づきでしょうが、「過去問は9月から!」というのは、この手順の③のみをやるということなわけです。
一方で、上記の手順①~③をすべてこなし、過去問の使い方①~③を入試本番までのスケジュールの中でうまく組み込んで使っていくことで、「過去問は9月から!」に忠実な受験生よりも格段に合格確率を高めていくことができるわけです。
さぁ、過去問を有効活用しよう!
というわけで、「過去問は9月から」という言葉にとらわれず、できるだけ早期に「使い方②」「使い方③」の過去問の使い方を活用して、先手先手で「自分自身の成長・強化」を図っていきましょう!
もし塾に通っていて「時間的になかなか過去問に手が回らないよー」という人や、「この過去問の使い方だけでもサポートしてほしい」という人は、「使い方②」「使い方③」にフォーカスした過去問演習講座も行っているので、ご希望の場合は下記のX(旧Twitter)のDMにてご連絡いただければと思います。
というわけで、今回はこのあたりで。
最後に過去問へのリンクも再掲しておきます↓
また、もし今後もブログを読みたいと思っていただけましたら、ブログのブックマーク、もしくは更新情報を投稿しているX(旧twitter)のフォローをよろしくお願いいたします。
【X(旧twitter)】
・ たくと@慶應付属中専門の塾講師・家庭教師
( @tact_roadtokeio )
ではでは、だいぶ長くなりましたが読んで下さってありがとうございました。
また次回、お会いしましょう!