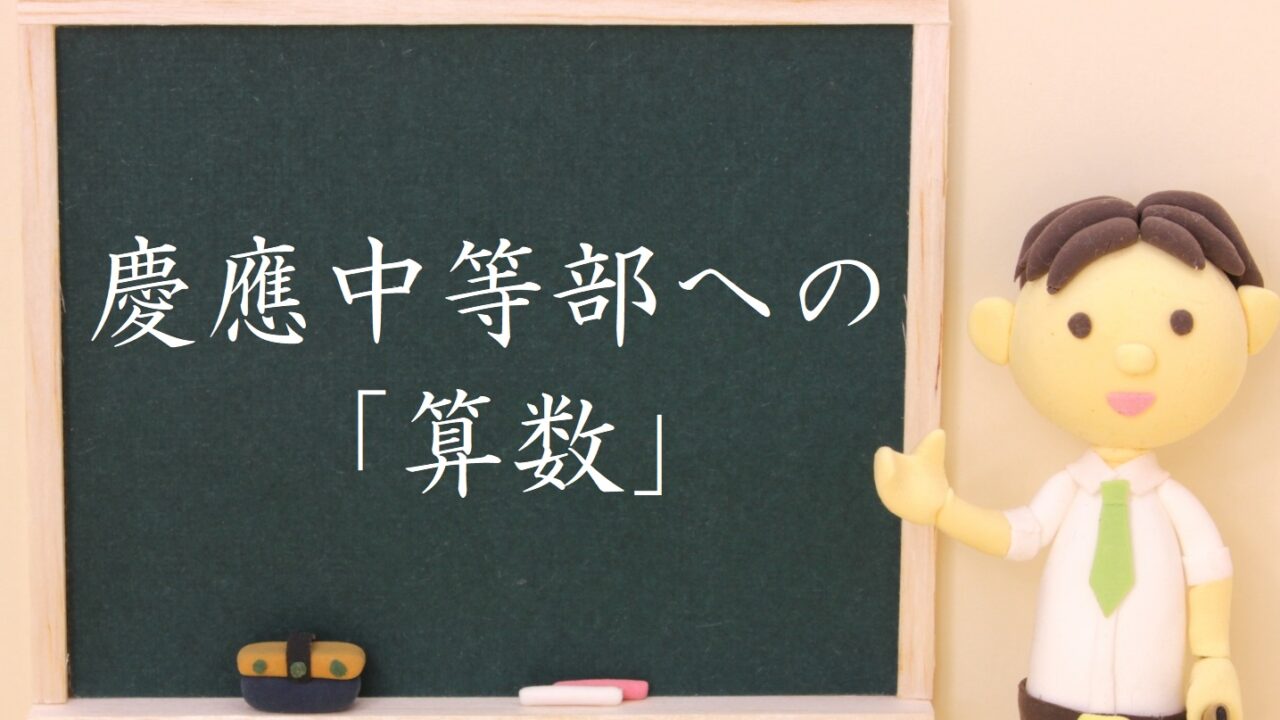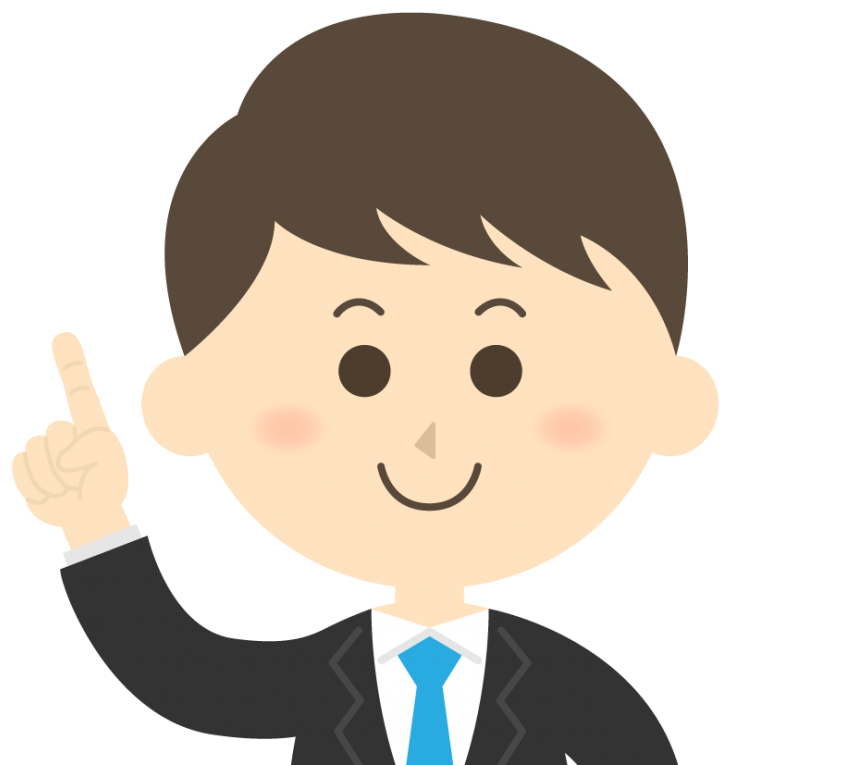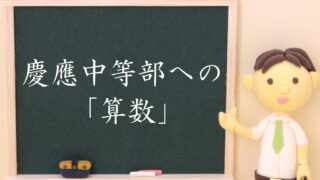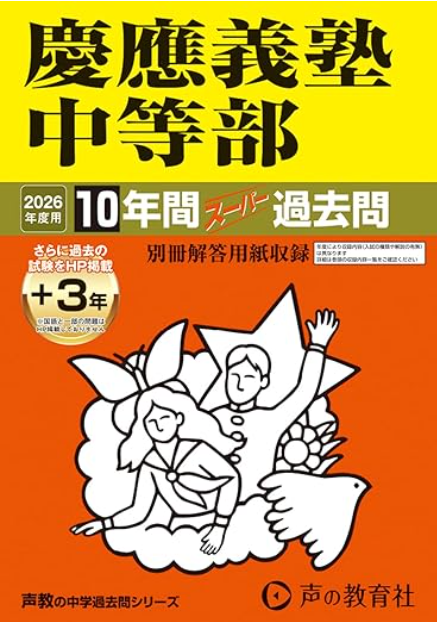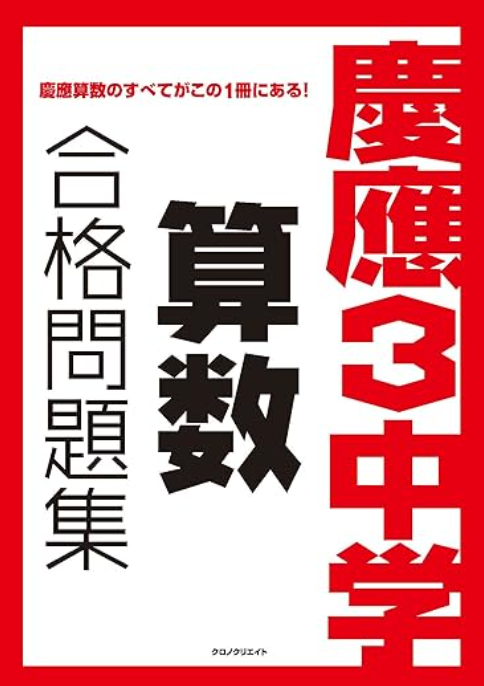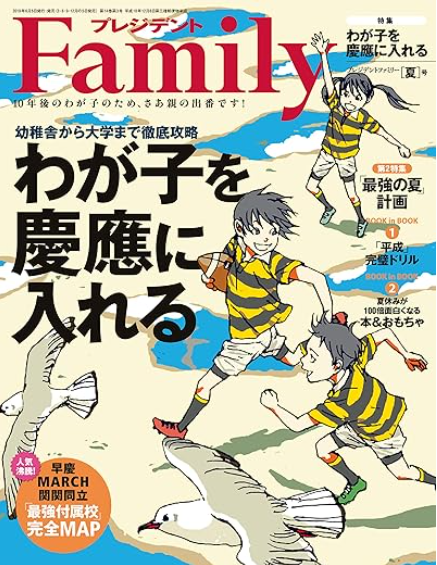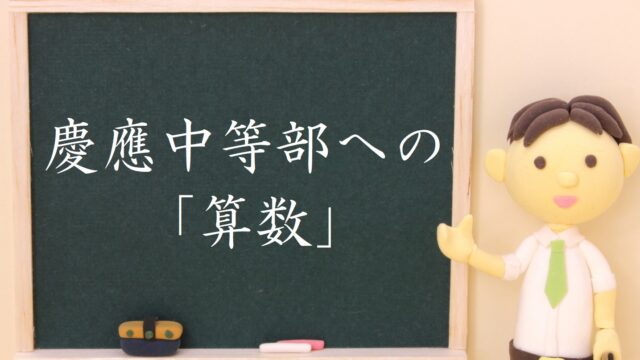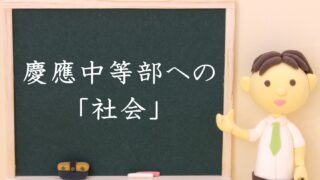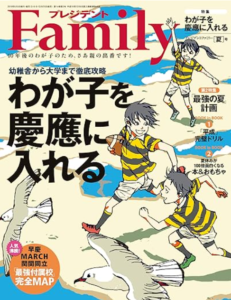このブログは、慶應付属中専門の塾講師・家庭教師をしているたくと( @tact_roadtokeio ) がお送りしております。
さて、今回は慶應中等部の2025年度入試(令和7年度入試)の算数の過去問分析を行っていきます。
今回の記事は、「慶應中等部の算数は簡単!」という誤認識が合格を大きく遠ざけてしまうよ、と書いた前回の記事(↓)が前提となるので、もしまだ読んでいない方がいましたら、そちらをまず読んで頂けたらと思います。
また、その記事の中で、慶應中等部の算数を
- 足切り問題となる「7割問題」
- 合否を分ける問題となる「3割問題」
の2つに分類することの重要性も併せて書いており、今回の2025年度(令和7年度)入試の算数過去問分析もこの分類に基づいています。
また、問題自体は記載していないので、過去問をお手にしながら見て頂けたらと思います。過去問は声の教育社のものを購入するか、四谷大塚の過去問データベースを参照するのが良いかと思います。(過去問データベースは解説がないので、声の教育社の過去問の方がオススメ。)
では、さっそくいってみましょう!
慶應中等部の例年の問題構成
2025年度入試(令和7年度)入試の分析をするまえに、まずは慶應中等部算数の例年の出題傾向を見てみましょう。
慶應中等部の算数は例年、大問6個~7個の構成になっています。
そしてこれらの大問は、「大問1~3」と「大問4以降」の2つに大きく分けることができます。
大問1~3に関してはほぼ毎年同じ傾向で出題されており、大問1は計算問題+文章題小問、大問2は文章題小問、大問3は図形小問となっています。
- 大問1:計算問題+文章小問
- 大問2:文章題小問
- 大問3:図形小問
大問4以降は個別の問題が出題され、年度によって内容は変わります。
- 大問4以降:個別の大問
この傾向はあらかじめ把握しておきたいところです。
ではいよいよ、2025年度(令和7年度)の慶應中等部算数を大問ごとに分析していきましょう!
2025年度(令和7年度)慶應中等部の算数分析【内容・配点・難易度・時間配分】
【大問1】計算問題2問+文章小問3問
慶應中等部2025年度算数の大問1は、2024年度と同様に計算問題2問+文章小問3問という構成でした。
それぞれの問題の内容・配点(推定)・難易度・時間配分は以下の通りです。(時間配分は自分の指導している生徒さんの場合のもので、塾のカリキュラムで学んでいる子の場合は+30秒くらいを目安にすると良いかと思います。)
| 大問 | 小問 | 内容 | 配点 | 難易度 (易1→5難) | 時間配分 (目安時間) |
| 1 | (1) | 計算(順算) | 4点 | 1 | 1:30 |
| 1 | (2) | 計算(逆算) | 4点 | 1 | 2:00 |
| 1 | (3) | 約数・倍数 | 4点 | 1+ | 1:00 |
| 1 | (4) | 場合の数 | 4点 | 1+ | 1:00 |
| 1 | (5) | 約数・倍数 | 4点 | 1+ | 1:30 |
大問1で出題された合計5問はすべて難易度としては低めで、すべて7割問題(足切り問題)です。
なので、ミスせずに確実に満点を確保することが必要ですが、それはあくまで最低限の話で、ポイントになるのは時間です。
大問1全体の目安時間は合計7:00(苦手な人は9:30)なので、のんびり解いているとあっという間に時間を消費して、大問2以降で使える時間を失ってしまい、高得点勝負の戦いから脱落してしまうことになります。(慶應中等部算数は最低でも8割を確保する必要あり。)
すなわち、「普段の学習の時からダラダラと解かず、頭をフル回転させながらスピーディーに解いている子なのか?」を問うているのがこの大問1だと言えます。
【大問2】文章題小問5問
慶應中等部2025年度の大問2は、2024年度と同様に文章題小問5問の構成でした。
それぞれの問題の内容・配点(推定)・難易度・時間配分は以下の通りです。(時間配分は自分の指導している生徒さんの場合のもので、塾のカリキュラムで学んでいる子の場合は+30秒くらいを目安にすると良いかと思います。)
| 大問 | 小問 | 内容 | 配点 | 難易度 (易1→5難) | 時間配分 (目安時間) |
| 2 | (1) | 割合(相当算) | 5点 | 1 | 1:30 |
| 2 | (2) | 速さ | 5点 | 2 | 2:30 |
| 2 | (3) | 比(倍数算) | 5点 | 2 | 1:30 |
| 2 | (4) | ニュートン算 | 5点 | 2 | 2:00 |
| 2 | (5) | 比(自転車の前輪・後輪) | 5点 | 2+ | 2:00 |
大問2に関しては、(1)~(4)の4問が7割問題(足切り問題)、(5)のみが3割問題(合否を分ける問題)でした。
(5)は「頭を使って考える」という算数の基本ができていれば簡単な問題ですが、多くの塾で行っているパターン化学習(頭を使わずパターンを覚えて解かせる学習法)で学んでいる子にとっては難易度がかなり高く感じる問題です。
慶應中等部では、(5)のような、一見簡単そうに見えるけど「ちゃんと頭を使えているのか?」を問う問題が頻出です。
ちなみに、(5)で苦戦する場合は、(3)でも苦戦する子が多いです。この(3)と(5)を落とす場合は、算数の取り組み方を見直す必要があるでしょう。(脱パターン化学習を目指しましょう。)
【大問3】図形小問4問
慶應中等部2025年度の大問3は、こちらも昨年と同様に図形小問4問という構成でした。
それぞれの問題の内容・配点(推定)・難易度・時間配分は以下の通りです。(時間配分は自分の指導している生徒さんの場合のもので、塾のカリキュラムで学んでいる子の場合は+30秒くらいを目安にすると良いかと思います。)
| 大問 | 小問 | 内容 | 配点 | 難易度 (易1→5難) | 時間配分 (目安時間) |
| 3 | (1) | 平面図形(角度) | 5点 | 1+ | 1:00 |
| 3 | (2) | 平面図形(比と面積) | 5点 | 1+ | 2:00 |
| 3 | (3) | 平面図形(円の一部の面積) | 5点 | 1 | 1:30 |
| 3 | (4) | 立体図形(回転体の表面積) | 5点 | 2+ | 4:30 |
4問とも難易度は低めですが、慶應中等部算数恒例の回転体の表面積を求める(4)は、ミスしやすい&時間を浪費しやすい(油断してるとあっという間に10分とか経ってしまう)ので、この問題を目安時間内に正答できるかがポイントになります。
というわけで、大問4に関しては(1)~(3)が7割問題(足切り問題)、(4)が3割問題(合否を分ける問題)となっています。
【大問4】水量問題(水量とグラフ)
慶應中等部の大問4以降は、小問集合ではなく単独大問です。
2025年度の大問4は、水量とグラフの問題でした。小問数は2問。
それぞれの問題の内容・配点(推定)・難易度・時間配分は以下の通りです。(時間配分は自分の指導している生徒さんの場合のもので、塾のカリキュラムで学んでいる子の場合は+30秒くらいを目安にすると良いかと思います。)
| 大問 No | 小問 No | 内容 | 配点 | 難易度 (易1→5難) | 時間配分 (目安時間) |
| 4 | (1) | 1分あたりの増加水量の計算 | 5点 | 1+ | 2:00 |
| 4 | (2) | 水量グラフの分析 | 5点 | 3+ | 3:00 |
大問4に関しては、(1)が7割問題(足切り問題)、(2)が3割問題(合否を分ける問題)でした。
(2)は、「注いでいる水量を変えたタイミングはどこなのか?」を分析するところから始めるべき問題ですが、パターン化学習をしているとその思考にならず、「なんか言ってることがよく分かんない問題」と捉え、それっぽい計算を紡ぎ出してしまいます。
そういう意味で、「頭を使いながら問題と向き合えているのか否か」を問いたい中等部の意思が表れている問題とも言えるでしょう。2025年度算数の中で最もキーとなる問題です。
【大問5】条件整理(投票)
慶應中等部2025年度の大問5は、「確実に当選するために必要な得票数」を求める条件整理の問題でした。小問数は3問。
それぞれの問題の内容・配点(推定)・難易度・時間配分は以下の通りです。(時間配分は自分の指導している生徒さんの場合のもので、塾のカリキュラムで学んでいる子の場合は+30秒くらいを目安にすると良いかと思います。)
| 大問 No | 小問 No | 内容 | 配点 | 難易度 (易1→5難) | 時間配分 (目安時間) |
| 5 | (1) | 当選確実に必要な得票数 | 5点 | 1 | 0:30 |
| 5 | (2) | 当選確実に必要な得票数 | 5点 | 2 | 1:30 |
| 5 | (3) | 当選確実に必要な得票数 | 5点 | 3 | 2:00 |
大問5に関しては、(1)と(2)が7割問題(足切り問題)、(3)が3割問題(合否を分ける問題)でした。
(1)に関しては、実際は15秒くらいで終わる問題でしょう。
(2)と(3)に関しては、(2)は解けたけど(3)が解けない(もしくは解けたけど「なんかすっきり解けた気がしない」)という受験生が多いかと思います。
この問題に関しては、解けた・解けない云々よりも(解き方云々よりも)、(2)と(3)の本質的な違いが何なのかを言語化できるか(考え方を言語化できるのか)がポイントです。この言語化ができていないと、(3)を解いている途中で(2)の自分の答えに懐疑的になって(2)に戻ることになります。
「解き方」ではなく「考え方」自体を正面から問うこの(3)は、大問4の(2)と同様に2025年度算数の中で最もキーとなる問題です。
【大問6】平方数の和
慶應中等部2025年度の大問6は、平方数の問題でした。小問数は2問。
それぞれの問題の内容・配点(推定)・難易度・時間配分は以下の通りです。(時間配分は自分の指導している生徒さんの場合のもので、塾のカリキュラムで学んでいる子の場合は+30秒くらいを目安にすると良いかと思います。)
| 大問 | 小問 | 内容 | 配点 | 難易度 (易1→5難) | 時間配分 (目安時間) |
| 6 | (1) | 平方数(ルールの把握) | 5点 | 1 | 1:00 |
| 6 | (2) | 平方数(3つの平方数の和で表せる数) | 5点 | 5 | 6:00 |
大問6は、(1)が7割問題(足切り問題)、(2)が3割問題(合否を分ける問題)でした。
ただ、(2)に関しては難易度がかなり高く、時間内に解くことはかなり難しいので、差が付きにくい問題です。算数が超得意な人向けの問題と言えるでしょう。
大問6の全体感としては、「平方数」という概念を習っていない受験生を想定して、まずはリード文で平方数の説明がなされています。
(1)は、そのリード文の内容を把握できたかという問題で、難易度はかなり低いです。よく「うちの子は算数が苦手なので後半の大問は捨てて前半に集中させたい」という親御さんがいますが、中等部では後半の大問の(1)で難易度の低い問題が出ることがかなり多いので、この方針は絶対にやめるべきです。(これは大問4以降のすべての単独大問に当てはまることです。)
(2)は、3つの平方数の和で表せない数は、1~100までの整数の中で何個あるかという問題。場合の数の要素も含んでおり、難易度はかなり高いです(塾の先生でも数学的な鍛錬がないと苦戦するでしょう)。普段の学習の際は必ず理解できるようにしたいですが、試験本番では捨て問とするのもありかもしれません。
ちなみにこの(2)は、数学的に言えば「ガウス・ルジャンドルの三平方の定理(三平方和定理)」というものが背景になっています。(この「ガウス・ルジャンドルの三平方の定理(三平方和定理)」については別記事で詳しく書く予定です。少々お待ちを。)
2025年度入試(令和7年度入試)の「3割問題」(合否を分ける問題)
以上でみたように、2025年度(令和7年度)の慶應中等部の算数において、合否を分ける「3割問題」は以下の5問でした。
【慶應中等部2025年度(令和7年度)の「3割問題」】
- 大問2 (2)
- 大問3 (4)
- 大問4 (2)
- 大問5 (3)
- 大問6 (2)
配点で言うと、5点×5問=25点分。
つまり、2025年度の慶應中等部の算数は、この25点満点の試験だと捉えてください。
そしてこの25点分を如何に取るかにフォーカスして、対策を講じていきましょう。けっして、75点分の問題に一喜一憂したり、その取りこぼしをなくすために大半の時間を使うような学習をしないようにしましょう。
慶應中等部の算数で合格を目指すうえでオススメの参考書
最後に、慶應中等部を目指すうえでオススメの問題集を紹介しておきます。(普通部・湘南藤沢中等部志望の方にもオススメ。)
慶應3中学算数合格問題集
(クロノクリエイト)
この「慶應中学算数合格問題集」は、慶應中等部・慶應普通部・慶應湘南藤沢3校で過去に出題された算数の問題を単元ごとに分けているのがオススメな理由です。単元ごとに重点的に学んだり、苦手分野の克服にとても有効なんですね。
単元ごとの学習が必要な方は、ぜひ活用してみましょう。
.
というわけで、今回はこのあたりで。
もしまた読みたいと思っていただけましたら、ブログのブックマーク、もしくは更新情報を投稿しているX(旧twitter)のフォローをよろしくお願いいたします。また、指導依頼に関してはもX(旧twitter)のDMにご連絡いただければと思います。
【X(旧twitter)】
・ たくと@慶應付属中専門の塾講師・家庭教師
( @tact_roadtokeio )
ではでは、読んで下さってありがとうございました。
また次回、お会いしましょう!